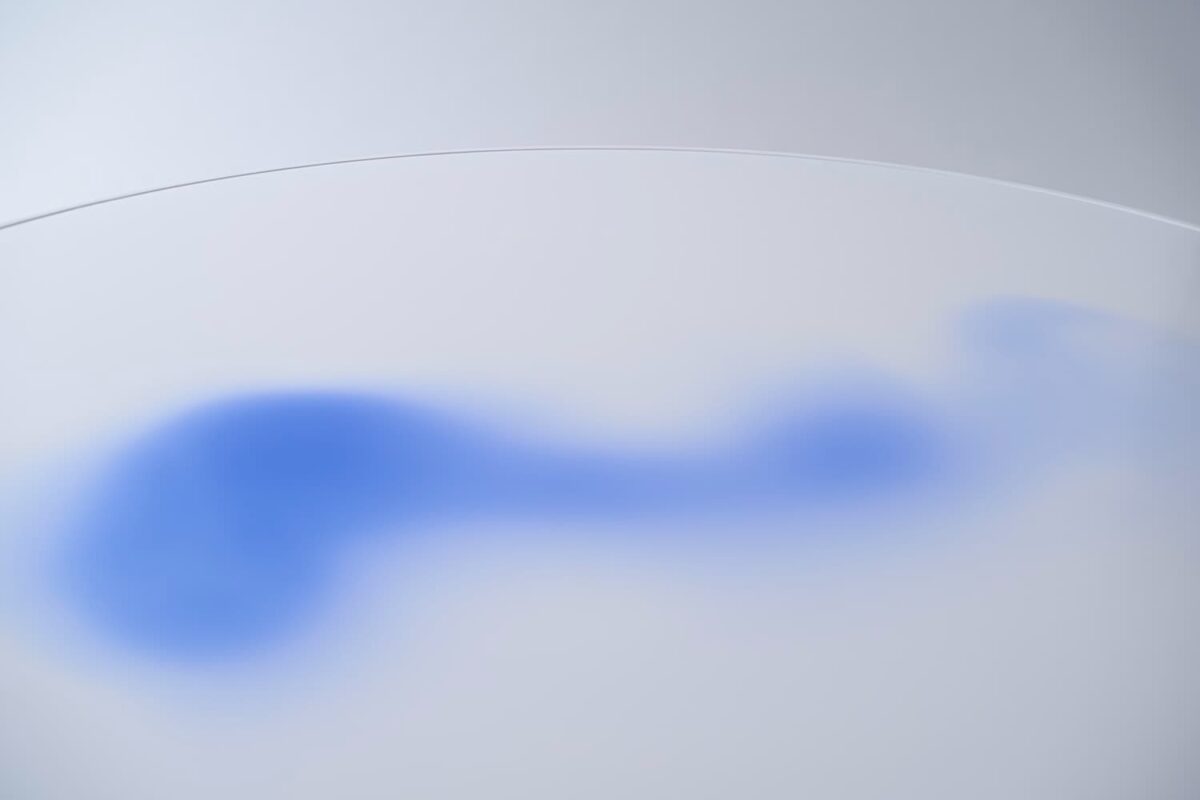林登志也氏と安藤北斗氏が創立したwe+(ウィープラス)はこれからのデザインの新定義を作り出すコンテンポラリーデザインスタジオだ。自然現象や社会環境を繊細に捉え、定義づけられる以前の感覚や価値観、違和感を美しく形にしていく。一般的に目にすることができる仕事には、ラグジュアリーブランドのウィンドウディスプレイや研究に基づいた展示発表、インテリアデザインなどがある。
それらの作品に到達するまでのアプローチは、一般的な逆算からなるデザイン手法とは異なり、アーティスティックリサーチという手法を軸にした仮説やフィールドワーク、実験、検証を積み重ねてたどり着いている。さらに、結論としての作品は息を呑むほどに美しい。

Drought
コンテンポラリーデザインからにじみ出る社会の断片
彼らが手掛けるプロジェクトの手順やアウトプット、コンセプトに至るまで一貫しているのは、絶対的な価値観に対する懐疑心だといえる。自然と歴史への畏怖と尊重を持ちながら、体制・手法・ルールなどの全ての当たり前に疑ってかかる。彼らの仕事は、人間という存在が作り出したシステムの脆さを雄弁に語り、それは昨今のデザイン界の潮流である“コンテポラリーデザイン”というジャンルにふり分けることができる。
コンテポラリーデザインとは、大量生産を前提としないデザイナーが目立ち始めた2000年代から徐々にデザイン界に沸き起こった動きであると解説してくれたのは、デザインジャーナリストの土田貴宏氏だ。スターデザイナーが席巻していた時代からリミティッドエディションの時代へとデザイン史が移り変わり、やがて「デザインという言葉が一層幅広い場面で使われ、デザイナーの活動形態も、求められる役割も、アウトプットの手法も多様化」し、「サービスやシステムのように形を持たない物事がデザインに含まれると主に、スペキュラティヴデザインのような問題提起型 のアプローチも広まって」新しい時代の新しいデザインの動きが生まれた。コンテンポラリーデザインは「更新されるデザイン」であり「過去の規範や枠組みをいかにこえるかが主要な価値を作っていく。ゆえに素材、技術、構造、機能などに加えて、コンセプトの革新性と独創性が重視される」と『デザインの現在コンテンポラリーデザイン・インタビューズ』(土田 貴宏 著/ PRINT&BUILD社)において土田氏が定義してくれている。


Panpuri ©Masayuki Hayashi
規範を崩すのは勇気がいることだ。彼らの基盤を作り上げたのはなんだろうか。コー・ファウンダーの安藤氏は、教員だった両親にリベラルに育てられたことではないかと推測する。
「両親は、例えば学校教育を真正面から受けとめるんじゃなくて、ちょっと違った切り口で受け入れてもいいのではなかろうか、といつも言っていて。そのせいか、“1+1=2”という回答に限らないでもいいんじゃないかとは、小さい頃からずっと感じていましたね」
高校では福田繁雄氏の作品集が置かれる美術準備室に屯し、ラディカルな(忌野清志郎の楽曲「ぼくの好きな先生」のような)教師の影響もあり、武蔵野美術大学の空間演出デザイン科に入学。スーパーポテトの杉本貴志氏や小池一子氏らが教鞭をとる環境で視点の持ち方を養った。1960年代のフルクサスの考えに傾倒し「既存の文脈に対するカウンターとしてアートがありうる」こと、オノ・ヨーコの作品などに影響を受ける青年時代を過ごした。

コー・ファウンダーの林氏は富山県から大学に進学後、舞台芸術やものづくりに携わりながらも、社会に出て経済活動に入っていくことに違和感を感じていたという。
「20年以上前から世界中で環境破壊が叫ばれている反対側で企業が普通に経済活動を続けて、売り上げや利益がどうだとかと話をしている。そのギャップへの折り合いがつけられなくてずっとモヤモヤした気持ちを持ち続けたままいたのですが、東北地方の県の仕事をきっかけに出会った縄文時代に光明を見たんです」
「縄文時代は1万2千年続いたと言われていて、出土した高技術な土器から推測すると、造型を追いかけられるほどの余力を持ちえるほどに安定した豊かな暮らしがあったことが想像できる。“違った方向”に振り切りすぎている現代に、あらためて縄文のエッセンスを少しずつ自分に取り入れると活きてくるんじゃないかなと考えたんです」

リサーチに立脚するwe+のアーティスティックリサーチとは
「一般的な“ジェネラルリサーチ”は、第一段階の“デスクトップリサーチ”によって情報を集約させます。デザインリサーチっていうのは多分ちょっと違っていて、リサーチする対象物を極めて客観的に分析していって、要素を抽出していく形だと思うので、そこにあまり主観性は入ってこないんです。それに対してアーティスティックリサーチは、自分たちの視点で切り抜くことができるので、自分たちの属人性や経験則によって何が面白いのか、面白くないのかが決まってくる、極めて主観的な方法だとも言えるのではないかと」(安藤)
「アーティスティックリサーチによる自分たちの特異な点があるとするなら、それは伝え方の工夫だと思っています。媒体にかかわらず五感に訴えかけるような、感覚を総動員させて自分たちが得てきたものを伝えることが、アーティスティックリサーチのアーティスティックたるところだと自負しています」(林)
2人での活動が始まったのは、2006年頃。東京都世田谷区の中学校校舎を再生した『世田谷ものづくり学校』の一角。人口が減り産業がシュリンクしていく中で、自分たちのものづくりはどうあるべきか。そんな危機感を持つと同時に、ヒエラルキー色の強い業界で、自分たちの「山」はどこなのかと自問自答をしながら悶々と、実直なフィールドワークを続けていた。
コンテンポラリーデザインは時代のカウンター
ターニングポイントとなったのは2014年のミラノデザインウィークにKAPPES名義で出品した『MO- MENTum(モメンタム)』がデザインメディアでベスト10作品に選出されたことだ。ここで、フランス人のキュレーターが発した“コンテンポラリーデザイン”という「山」に出会う。そこから様々な人に会い咀嚼をするうちに、数年かけて自分たちのステートメントとなった。
「コンテンポラリーデザインとは、時代ごとのデザインの本流という同じ軸の中ではなく、今までになかった視点や切り口、考え方で支流を作って更新していくということだと思っています。90年からの潮流が2010年代に本当に大きくなりましたし、メインストリームに対する反動みたいなものはずっと時代ごとにありましたが、日本は世界に比べて主流の力が強く、同調圧力的なものを民族的に持っている。違和感の根源であるそのことに気づいたのは、ミラノに行くようになってからですね」
彼らが本流へのカウンターである背景にはデザインの師匠を持たなかったということも関係しているという。自身で自分たちのスタイルを作っていったぶん紆余曲折はあったが、そのおかげで軸を固めることができ、ユニークな作品につながった。彼らの仕事が魅力的なのは、リサーチに主軸を置き発展させたことが要因なのかもしれない。
彼らが“アーティスティックリサーチ”と呼ぶ取り組みは、目的でも手法でもなく全体を指すもので、体験の蓄積でありながら芸術表現である。
2022年に行った霧をテーマにした『Nature Study:MIST』では、リサーチの過程を展示することを試みた。これが、単なるリサーチの成果発表を超える展示となり、デザイン業界のみならず、別のフィールドへも届くほどの強い手応えを感じたという。このように、アウトプットまでの全てのワークから導き出されるアーティスティックリサーチは、眼の前の物質や現象に対峙して実験や深堀りを繰り返すうちに、自然とアウトプットへと導かれていくのだそうだ。

Nature Study © Masayuki Hayashi


Nature Study © Masayuki Hayashi

「物を作る限りは共感してもらいたいですよね、届けるものだから。ただその人がすごくハッとするとか、心が震えるとか、そういう状態になって欲しいと思ったときに、僕らが見ていて一番強いのは自然現象だなと思っているんですよね。やはり昔から自分たち人類が生まれた頃から身の回りにあって、そういうものとともに生きているので、自然現象のハッとする瞬間を仮に切り取って、それを否定する人はほぼいないのではないかなと。共感を考えたときに、自然の揺らぎとか不確実なところをいかに捉えるのか、は考えています」(林)
「揺らぎや不確実性といった不均一がもたらす歪さのほうが美しく見えちゃうんですよね。真っ白な壁には共感しにくいけれど、表情のあるコンクリートのほうがずっと見ていられる」(安藤)

Reform © Masayuki Hayashi
消費社会の都市鉱脈、現代の民藝という視点
もちろん、彼らにとって表現の軸となるのは自然からのインスピレーションに限ったことではない。廃棄物を都市の素材と見立てた作品が近年、広く話題を呼んでいる。代表的なのは、東京で回収された使用済みの発泡スチロールを使った『Refoam』や、再生利用率53%の産業廃棄物の中でも特に分解が難しい混合廃棄物を拾い上げ作られた『Remains』、そして東京で回収された使用済みの銅線を使った『Haze』だ。都会のゴミを使った作品は、土着のものを使って素材と人の関係を再構築し、新たな価値を与える試みであり、自然循環を無視した採掘やリサイクルするための移動が環境負荷を起こしている事実に対するカウンターでもある。これらもまた、純粋な美しさを放ちながら、社会に対する問題解決を提示していると同時に、民藝が土地の文化風習に強く紐づいているように、東京のデザインスタジオに対する都市鉱脈として廃材という素材に対峙したものだ。



Remains ©Masayuki Hayashi
社会の接続詞たる存在でありたい
「デザイナーが社会に求められてることって刻々と変化してると思うんです。今自分たちが行っているプロジェクトは半分意識的にあるいは半分無意識的に社会というものを日々観察することで受けた影響がきっとすごく素直に出ている結果なんだろうなと思ってます。社会の情勢に合わせて自分たちの役割が変わるという前提に立つと、5年後あるいは10年後、20年後には何をしているかも全然想像できないんじゃないかな」(安藤)
「僕らは社会を変える大きな歯車にはならないけれど、 一番最初に回り始める小さな歯車みたいな役割ならできるんじゃないかなって気はするんです。ここが回らないとその次は絶対回らないみたいなものってきっと世の中たくさんあると思うんですよね」(林)
「小さい歯車から大きい歯車、そういう意味で確実に社会の接続詞たる存在でありたいね。ただ、その一番最初のきっかけや視点を作っていくことに対してはかなり意欲的にコミットしていると思っています。自分たちの中で浮かんだ疑問や視点をどんどん作って、どんどん投げかけていきたいですね」(安藤)
interviewed in May, 2023

デザインスタジオ
we+
林登志也氏と安藤北斗氏が2013年に設立したコンテンポラリーデザインスタジオ。
プロダクト、インスタレーション、グラフィックなど、多岐にわたる領域のディレクションとデザインを行い、テクノロジーや特殊素材を活用した実験的なアプローチを追求。自然現象や社会環境を繊細に捉え、定義づけられる以前の感覚や価値観、違和感を美しく形にして国内外で高い評価を受ける。
WEBSITE